「安保3文書」改訂と大軍拡路線を粉砕するためにともに闘おう!
1月23日、やっと通常国会が開会した。昨年末からの経緯を再確認しておこう。
昨年12月16日、岸田内閣は従来からの専守防衛の原則を根本から覆す「安保3文書」を国会審議なしに閣議で決定した。そして恰も決定事項だと欧州へ宣伝に回った。まさに許されざる暴挙だ。さらに1月12日、米国で日米の外務・防衛閣僚による安全保障協議委員会(2+2)を開き、日本の敵基地攻撃能力の「効果的な運用に向けて日米間の協力を深化させる」と合意。その後に発表された共同文書には、日本は防衛費増額で防衛力を根本的に強化する決意を示し、当然のことながら米国は「強い支持」を表明したとある。
翌13日に岸田首相は、バイデン大統領と会談を行う。共同声明では「今日の我々の協力は法の支配を含む共通の価値観に導かれた、自由で開かれたインド太平洋と平和で繁栄する世界という共通のビジョンに根ざした前例のないものである」と自画自賛する。
しかしそもそもこのような防衛方針の大転換は、国会論議なくしてはできないものだ。しかも2023年度から5年間の防衛費を43兆円とし現行計画の1・5倍以上に増額するというのだから、恐れ入る。この予算増額に関しても財源についての国会議論はない。
今回の目玉である敵基地攻撃能力を持つということは、同時に「敵」から明確に攻撃されることにもなる。一撃で「敵」を粉砕できない以上、攻撃された「敵」は必ず全力で反撃してくるのが戦争の現実である。どうしてこの明々白々な関係に言及しないのか。
元外交官の孫崎享氏は、太平洋戦争でも当初の真珠湾攻撃こそ成功したものの、ために米国は全面戦争に突入し、その後の日本は完膚無きまでに殲滅されたことを指摘する。
現在、想定の「敵」とは中国だが、最近の台湾有事とは米中覇権争いの結果である。そもそも最近まで日米は「中国は一つ」を尊重してきた。国連から中華民国を追放したのは米国だ。台湾と国交断絶したのは日本だ。何たる掌返し。信義に欠けた行動ではないか。
まずは岸田内閣を有権者無視、国会軽視の観点から徹底して追及すると共に、敵基地攻撃能力や財源問題に関して大いに論戦する必要がある。さらに今こそ、日本は日中国交回復の原点に立ち返り、中国との信義を堅持するように迫っていくことが重要なのである。
まさに今通常国会は、日本の歴史的な転換点と目される国会となる。ともに闘おう!(直)
〝賃上げムード〟?いや、闘いとるぞ!――生活防衛の二正面作戦――
2月中旬から〝春闘〟が本格化する。足元では物価上昇が続き、生活は圧迫されている。
賃金とは、上げてもらうものではなく、闘いとるべきものだ。
足元ばかりでなく長期の目標も明確化して、生活防衛を勝ち取っていきたい。
◆2、圧迫される生活
物価高が止まらない。
昨年11月の物価上昇は3・7%。12月は4・0%だ。政府の見通しでは、22年度は3・0%、23年度は1・7%とされている。黒田日銀の10年でも〝達成〟できなかった2%の物価上昇が、この1年足らずでその2倍もの上昇だ。毎日の生活実感では、2~3割上がっている感じもしてしまう。年明け以降も多くの品目で値上げが予定されている
こんな状況の中、企業もすでに賃金引き上げを行った企業もあり、また春闘での賃上げを表明した企業も出てきた。岸田首相も「物価上昇以上の賃上げ」「構造的・継続的な賃上げ」を掲げる。経団連も「賃上げは企業の責務」と言う。
が、現実には賃金は上がっておらず、実質賃金は下がり続けている。安倍元首相が言い出して何年も続いた〝官製春闘〟も、全てかけ声倒れだった。
なぜ日本の賃金は長期にわたって低迷し続けているのか。それにはそれなりの理由がある。
◆差別・分断を強いる賃金体系
まず現実を見ていきたい。
近年、先進国クラブとい言われるOECD諸国のなかで、日本だけ賃金が上がっていない。〈図表1〉を見ば歴然だ。
 図表1
図表1その日本、企業の経常利益だけは順調に上がっている。企業の内部留保は、毎年のように積み上がり、21年度には500兆円を超えて過去最高に膨れ上がっている。株への配当増や自社株買いによる株価引き上げで、企業利益の株主還元は厚く行われてきた。全く逆に、人的資源=賃金への配分は抑制したままだ。〈図表2〉を見れば歴然としている。
 図表2
図表2この二つの図表だけでも明らかなように、日本では圧倒的に労働者を無視した分配構造ができあがっている。
なぜそうなってしまうのか。
その原因の一端が、日本独自の雇用・賃金形態にある。
欧米では企業横断的に形成されている労組と、同一労働=同一賃金を土台とした賃金・処遇方式が一般的だ。
一方、日本は〝日本的労使関係の三種の神器〟といわれる、終身雇用・年功賃金・企業内組合が基本型だ。OECD諸国で一般的なジョブ型雇用と同一賃金=同一労働とは対極的な、メンバーシップ型の雇用が普及しているのが実情だ。
その日本で一般的な雇用形態の中で多く採用されているのが、能力主義賃金を年功的に運用している〈図表3〉のような賃金体系だ。
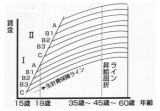 図表3
図表3この賃金体系モデルを一瞥すれば、大手企業の労働者・サラリーマンは、自社の賃金体系とさほど変わらないものだと直感できるだろう。この賃金モデルを見るだけで、日本の労働者・サラリーマンは、労働者どうしが団結して経営側、会社側に立ち向かうことができない賃金体系だと想像できる。
なぜなら、自身が昇給するためには、上位の昇給線に移行しなければならないが、その場面ごとに会社側の厳しい査定・選考が待ち受けていることを見せつけられるからだ。会社に刃向かえば、最下位の賃金カーブを強いられる。これでは世間並みの生活は出来ない。同時に、同年齢、同勤続の職場仲間と大きな賃金格差が付いてしまう。これは屈辱でもある。
こうした職能賃金システムの下では、毎年の春闘で500円コイン数枚のベアをめぐる労使の攻防で、エネルギーを投入できるわけがない。それより、万単位で月給が上がる上位級の賃金昇給線に昇格できる出世・昇任競争に力を入れた方が、どれだけ収入増になるか、一目瞭然だからだ。
日本の大手企業は、こうした職能給などで労働者を差別分断し、労働者の団結した闘争力をそぐ統治システムを採用しているのだ。
◆闘わない、闘えない労組
日本の企業は、日本的な労使関係と賃金政策によって、労働者が団結して企業に立ち向かうことを阻止するシステムを作り上げてきた。
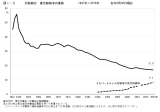 図表4
図表4〈図表4〉は、戦後の労組組織率の推移を示した図表だ。一目瞭然、労働者が組合に結集しない、できないという現実を示している。
労組の組織率は最高が1949年の55・8%、2022年には16・5%にまで落ち込んでいる。非正規労働者が拡大する過程で、組織率下落も加速している。
組織率だけではない。結果的に、日本の労働者は闘って要求を勝ち取るという存在になりきれないでいる現実を映し出している。
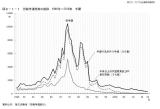 図表5
図表5労組組織率の下落とほぼ同じような下降曲線を示すのが、争議(ストライキなど)件数〈図表5〉だ。これも80年代後半以降進んだ経済のグローバル化と並行するかのように、争議行為が減少していく経緯が見て取れる。
要するに、非正規化を含めて、労働者が労組に結集し、団結して企業と対峙する、という関係が解体されてきたわけだ。端的に言えば、労働者を分断して闘争力を削ぐ企業・経営側による雇用・賃金システムの導入が功を奏した、ということだ。労働者側から見れば、労使の攻防戦に敗北を重ねてきた結果でもある。
◆押し付けられた低賃金構造
日本の職能賃金や成果給、年俸制などの賃金システムに対して、以前のような終身雇用と年功賃金を懐古する声もある。が、それは現実味がない。そもそも、日本の賃金システムは、いつの時代でも経営側主導の〝いつの時代でも低コスト〟だった。
戦後の右肩上がりの人口増で若者が多かった時代。そこでは遠い将来での高賃金と現実の若年時代の低賃金システム。要するに年功序列賃金で、これが総額人件費を圧縮できるシステムだったからだ。
高齢化社会の幕開けと低成長時代の80年代。年功賃金カーブの右肩下がりへの改変が財界の意向だった。現に、高齢労働者の右肩上がりの賃金カーブは、50才代以降、右肩下がりに改変された。
経済のグローバル化と輸出主導型経済への転換で、高コスト人件費が集中攻撃され、リストラが横行し、正規雇用の非正規化が強引に進められた。経団連の『新時代の日本的経営』(1995)だ。そこではすでに個々の企業が導入しつつあった非正規労働者の採用を、経団連の旗振りで強引に拡げられた。その結果が〝非正規4割時代〟なのだ。
いはば、非正規化と低賃金構造は自然災害などではなく、経団連主導の〝人災〟だったのだ。
◆賃上げムード?
足元の物価急上昇を受けて、岸田首相も経団連も賃上げの旗を振ってはいる。が、それが現実の賃上げに結びつくことはない。実際の賃上げを実施するのは、個別企業だからだ。経営側も労組側も、実権を持っているのは個別企業、個別組合だ。
その個別企業。それぞれの業種のトップ企業などは、企業イメージ向上の思惑もあって賃上げに積極的なポーズを示す場面もある。が、それが全企業での賃上げには直結しない。
個別企業は、自社製品の売り上げ増加のためにも、他企業の賃上げは歓迎する。が、企業間競争を考えれば、自社の労働コストを抑え低価格で売り上げを増やし、自社だけは大きな利益を上げたい、と考える。結果的に、こうした個別企業の思惑で、賃上げの動機は膨らまない。
仮に大手企業で賃上げが行われても、全労働者の7割を占める中小企業の労働者の賃上げが実施されなければ、全体の底上げにはならない。そのためには、下請けや系列会社の納品価格の引き上げが不可欠だ。
しかし、現実には大企業はそれを妨げている。大企業・親企業が、子会社・取引会社の単価引き上げを認めないからだ。現に、トヨタ自動車グループのデンソーなど13社が、納品会社のコスト上昇を考慮していないという独占禁止法の「優越的地位の乱用」に該当する恐れを理由に、昨年12月27日、公取委から社名を公表されているのが実態だ。
トヨタは、部品・製品を納入するグループ会社に、毎期のように納入単価の削減を〝要請〟してきた経緯がある。同じように、多くの大企業は、自社の利益確保を最優先に、下請け・関連会社のコストダウンを要求している。こんな構図では、末端の下請け・製品納入業者にまで、大企業と同じ賃上げなど出来るはずもない。
◆中長期の二正面作戦
目の前の課題としては、政府や財界の〝賃上げムード〟などに頼ることなく、生活防衛のための至極正当な要求である大幅賃上げを勝ち取る行動を全力で拡げていきたい。
が、それは労働者の闘いの緒戦に過ぎない。中長期的な課題としては、なんといっても〝日本的な労使関係〟からの脱却だろう。
まずは、職能給的な《競争賃金》から、〝同一労働=同一賃金〟という労働者が団結して経営側と対峙できるような《団結賃金》原則への転換だ。
第二は、《人に値札を付ける》メンバーシップ型雇用から、《仕事に値札を付ける》ジョブ型雇用への転換で、これは第一の転換とセットだ。
第三は、企業に従属した《企業内組合=会社組合》から、個別企業の枠外につくる組合、企業横断的に組織する《まっとうな労働組合》への転換だ。
このような中長期的な転換は、生半可な努力では実現できない。しかしそうした目標へ努力することなしには、現状の閉塞状況から脱出することは不可能だ。
外国では、物価高が続く米国で多くの州で賃上げストが実施され、成果を上げている。英国でも、物価高に対して鉄道・郵便・救急隊・看護師・教員・公務員など、大規模なストが実施された。フランスでも、年金改悪に抗して労働者のストライキも拡がっている。
一方、日本でも、アマゾンやウーバーなど外来職種の職場を含めて、小規模でも組合づくりやストライキが取り組まれている。闘うこと抜きに展望は切り開けないのだ。
長い、厳しい闘いになるが、行動を起こし、拡げていきたい。(廣)案内へ戻る
読書室 斎藤 幸平氏著『ゼロからの『資本論』』NHK出版新書 二0二三年一月刊
○本書は、マルクスが労働を物質代謝と表現したことを丁寧に解説しつつ、資本主義社会は商品という「物象」が人間を振り回す、「物象化」の世界であることを暴露・批判するとともに資本主義社会を克服するための新しいコミュニズム論を展開したものである○
『大洪水の前に』、『人新世の「資本論」』、そして『ゼロからの『資本論』』
二0二0年九月、既に約半年前に主著である『大洪水の前に マルクスと惑星の物質代謝』を刊行していた斎藤氏は、引き続き第二作目の『人新世の「資本論」』を現代資本主義が生み出した格差社会や環境破壊等の状況に抗し、満を持して出版したのである。
この本は、「気候危機の時代に、良い社会を作り出すための想像力を解放してくれるだろう」との斎藤氏の希望に応えるかのように、すぐさま四十万部を売り上げた。今なお五十万部に迫る勢いで売れているとのことだ。機を見るに敏で商魂逞しいNHKは、なんと二0二一年一月にはEテレの「100分de名著」番組において「カール・マルクス資本論」を取り上げ斎藤氏を講師に招聘することで、彼を一躍時の人にしたのであった。
斎藤氏の新著は、「100分de名著」のテキスト「カール・マルクス資本論」に大量加筆したものとの触れ込みだが、私の推察では、ある人達の非難を意識して書いたと考えられる部分がある。それがこの新刊書をさらに輝かせるものになっていると考える。
第1章では、「商品」振り回される私たちが生きている「物象化」した世界が論じられ、「使用価値」と「価値」とは何かが詳説されている。第2章では、過労死の問題は「労働」と「資本」、実は「労働力」と「資本」との労働時間を巡る闘いが根底にあることが解説される。第3章では資本主義が無駄な労働を作り出すと暴露される。第4章では資本蓄積が自然の回復力を破壊するとの批判がなされ、第5章は「グッバイ・レーニン!」と題され、ソ連は社会主義ではなかったとの斎藤氏の批判が、第6章ではコミュニズムが新たな観点から再評価され、「マルクスはユートピアの思想家である」と締め括られている。
西野勉氏と原野人氏の『人新世の「資本論」』非難
この斎藤氏をめぐっては褒める人あり、腐す人ありと人々の反応は人様々だ。ここでは典型的な反応として、私が本書の構成と関連すると推理する二人だけを挙げておこう。
まずはマルクス経済学者・高知大学名誉教授の西野勉氏。彼は、二0二一年十月発刊の大学紀要「高知論叢」に「斎藤幸平『人新世の「資本論」』集英社新書(二0二0年九月)におけるマルクス利用・援用の問題性 ―「脱成長コミュニズム」主張のための我田引水解釈・捏造・虚言・妄言について」の表題を持つ論文を掲載した。その立場は明確だ。
もう一人は、『牙を抜かれたマルクス主義―斎藤公平とマルクス・向坂・資本論』(時潮社二0二二年四月刊)を出版した原野人氏。私にはこれまでまったく未知の人である。
この本の著者略歴には、旧ソ連を天まで持ち上げてきた向坂社会主義協会の活動家で、新社会党の元理論担当中央執行委員であったとある。彼は、斎藤氏の思想を小ブルインテリの夢想、と一刀の下に切り捨てた。まさにスターリンの政治的断罪そのものである。
これらの二人は、要するに「斎藤君はマルクスの名を語りながら、恥ずかしげもなく講釈師のような嘘を述べているというほかはない」とする。彼らの拘りは実によく分かる。
しかしこんな反応でよいのだろうか。現代の日本社会の現状に対して、マルクスなら一体今何を書くだろうか、との斎藤氏の切実な問題意識が彼らにはまったくないのである。
先に挙げた西野氏は、斎藤氏の「本源的蓄積論」はマルクスを利用し、自らの「脱成長コミュニズム」主張のための我田引水解釈・捏造・虚言・妄言を連ねているだけだとの激烈な非難と、マルクスの「最晩年の真の理論的な大転換」などない、と激しい言葉で斎藤氏を論難する。自分こそ第一人者だとの自覚はよい。だが斎藤氏は少なくともメガ版編集に関わっている人なのだから、晩年のマルクスの研究ノートに関しては、未見の自分(西野氏)よりも詳しいのではないか、との謙虚な判断や推論が何故出来ないのであろうか。
また原氏も、ソ連崩壊や中国変質の根本原因は、「労働者階級の権力が大きく逸脱していったからだ」と説明する。だがその説明ではまったく説得力がない。問題は、なぜ、いかにしてソ連で労働者階級の権力が大きく逸脱していったかにあることは明白である。
斎藤氏は、現存「社会主義国」は資本家に取って代わって党や官僚が労働者の剰余価値を搾取していく経済システム、つまりソ連が国家資本主義であると明確にしたのである。
資本主義では生産手段の私的所有こそが問題で、生産手段を国有化して計画経済をすれば社会主義へと移行できるとする「マルクス主義」理解は、共産党や向坂社会主義協会のもので、ソ連体制イデオロギーに取り込まれた見解である。問題は、斎藤氏が言うように労働のあり方であり、労働者が搾取のない自由な労働のあり方を生み出すことにある。それを助けるのがアソシエーションであり、それこそがコミュニズムの具体化なのである。
斎藤氏を酷評する二人には、「人新世」に対する理解はない。人類が直面している危機についての鋭い問題意識もない。彼ら自身、「マルクス主義者」として一体何を考えているのか。この二人には、『大洪水の前に』以来の斎藤氏の「マルクスと惑星の物質代謝」論に対して何の言及もなく関心さえないのである。老残の極みとでも言うべきだろう。
地球と人類の未来は暗くなるばかりだ。ごく近い将来、資本主義のままでは人類社会そのものが絶滅の危機が迫っているのにもかかわらず、斎藤氏が提起するマルクス的な解決策に対しては、自らの「マルクス理解」に拘り続け、ただただ罵倒するだけなのである。
『大洪水の前に』刊行時から斎藤幸平氏は一貫して久留間学派である
こうした二人は捨て置いて私たちは前進しなければならない。本書については、既に久留間鮫造氏と大谷禎之介氏の学統を継ぐ佐々木隆治氏は「やや我田引水になりますが、斎藤さんの『ゼロからの資本論』→拙著『カール・マルクス』→拙著『マルクス 資本論』→岡崎次郎訳『資本論』という順番で読んでいくのが一番よいと思います」とツイートした。まさに斎藤氏を全面的に絶賛している。本書にはそれほど素晴らしいものがある。
私が最後に付け加えたいことは、斎藤氏自身が『資本論』への読書ガイドとして二つの著作を挙げていることだ。一つは、大谷禎之介氏が訳したヨハン・モスト『マルクス自身の手による資本論入門』。そしてもう一つは、『普及版 マルクス経済学レキシコン』。
この二つを挙げることで、斎藤氏は自らも久留間鮫造氏と大谷禎之介氏の学統を継ぐ者だとの名乗りを挙げた。このことで斎藤氏は西野氏の「我田引水解釈・捏造・虚言・妄言」論や原氏の「小ブルインテリの夢想」論に、無言ながらしっかりと反論したのである。
こうして旗幟を鮮明にした斎藤氏に対してこれらの二人は、本書を「マルクスはユートピアの思想家である」と締め括ったことをもって「小ブル」思想家の本性を自己暴露したと批判するのであろうか。閉塞状況に陥った時代の中で「マルクスはユートピアの思想家」と訴える斎藤氏の判断は、決して間違ったものではない。私はそのように判断する。
本書は刊行一週間で既に十万部を売り上げたという。是非皆様へ一読を薦めたい。(直木)
岸本美緒著『東アジアの「近世」』を読んで
●東アジアの「近世」
近世から近代への世界史の中で、中国をはじめとした東アジアの「近世」をどうとらえたらよいのか?
大塚久雄がイギリスの独立自営農民と毛織物マニュファクチュアを主眼に叙述したような「発展段階論」でも、川北稔がカリブ諸島の砂糖プランテーションと奴隷貿易から叙述した「世界システム論」でも、今ひとつうまく説明しにくいのが、東アジアの「近世史」ではないだろうか?
この問題に斬新な視点で挑戦したのが岸本美緒の『東アジアの「近世」』(山川世界史リブレット)である。
●銀の流れ
着目したのは「銀」である。この時期、東アジアには大量の銀が流入し、それを機に「大商業時代」が訪れた。流れは次のようになる。
南米のポトシ銀山で産出された銀は、いったん大西洋経由でヨーロッパに向かい「価格革命」をもたらした。しかし銀の流れはそこで終わらず、さらに喜望峰を回りインド洋を経て、中国に流入した。
これとは逆方向の流れで、メキシコ・アカプルコから太平洋をガレオン船に載って、フィリピン経由でも銀は中国に流入した。
さらに日本の石見銀山でも銀が産出され、ポルトガル商人を介して、やはり中国に流入した。
こうして西ヨーロッパの「大航海時代」と連動する形で、東アジアの「大商業時代」が開始されたのが、東アジア「近世」の特徴だというのである。
●生糸と薬用人参
では銀は何と交換されたのか?中国南部の江南では「生糸・絹織物」産業が盛んであり、それらをめぐって「倭寇」の活発な交易活動があった。
北方では遊牧民がやはり交易を求めて、明朝との軍事的衝突を繰り返しており、背景に「貂」(高級毛皮)や「人参」(薬用)に対する需要の高まりがあった。
●発展段階論争
中国の宋代から明・清期については、「近世説」を唱える内藤湖南等の京都派と、「中世封建説」を唱える東京(歴研)派の間に論争が繰り広げられてきた。
発展段階論の視点から、中国社会における自営農民やマニュファクチュアの成長に着目し、そこに資本主義の萌芽を見出そうとする問題意識があった。または「なぜ資本主義が成長できなかったのか?」と、マイナス条件を探し出そうと試みたとも言える。結局、こうした論争は実を結ばないまま、今日に至っているのが現状である。
岸本の近世論は、思い切って視点を変えたもので、実態に即した歴史叙述に近づこうとしているのは確かだろう。
●秩序の形成
やがて銀の産出量はピークを超え、大商業ブームは沈静化し、倭寇や北方民との紛争も収束し、中国の国家体制は安定化と秩序形成へ向かう。
ここから、近代化以前の中国社会に対する、二つのイメージが錯綜する。一つは「大商業時代」の活発な商人や職人の活躍する流動的な社会像であり、今日の「改革開放」「国家資本主義」の姿につながる。
もう一つは「専制国家」としての歴史叙述であり、現在の習近平政権における「独裁体制」や「覇権主義」の姿に連なる。
現代の中国は、この明暗両面を合わせ持っており、従来のような「専制」のみの中国社会像の延長だけでは、十分な理解は難しいのは確かだろう。
その意味で岸本美緒の提起は、東アジア「近世」像の見直しをせまるものである。(冬彦)案内へ戻る
軍拡増税、MMT増税は許さない!
岸田政権と与党の大軍拡路線は、それが増税を謳うならば大きな支持は得らることは難しいだろう。そのことを見越して、萩生田晃一や高市早苗(統一教会ずぶずぶコンビ!)など自民安倍派の残党は国債発行・国の借金政策で軍事費増の財源を賄うべきだと言っている。
この、借金依存の軍拡推進論の誤りと犯罪性は、第一にはそれが将来の税収の先取りであり、のちには大増税による大衆収奪(あるいはインフレを通した大衆収奪)を必然化せざるを得ないという事実を隠している点にある。流行の(というほどでもないが)MMTによれば借金など心配するに及ばず、日銀は政府の一部としてどんどん円札を発行することが出来るのだから財政限界など生じない、インフレも起きないと主張してきた。この応援団に力を得た安倍政権は財政膨張とそれを支える超金融緩和策を続けてきたが、インフレは発生した。
MMT派はこの事実をどのように言い繕うのだろうか。
安倍派や岸田首相はインフレは財政膨張・金融緩和策のせいではなく、米国の金利引き上げがもたらした円安が原因だ、ウクライナ戦争で原料・燃料などの物流・輸入困難が引き起こした等々と言い訳をしている。しかし円安は、財政膨張と金融緩和策が生み出したインフレ(つまり日本円の「価値」の低下)の結果であって、原因ではない。
また原料・燃料などの価格高騰は、世界の経済先進諸国が日本と同様にこぞって励んできた財政膨張と金融緩和策(インフレ政策)が拍車をかけた過剰貨幣資本・架空資本の膨張、その投機的行動が生み出した結果である。ここでも安倍派や岸田は原因と結果をあべこべに描いている。
また、借金をしての軍拡推進策の誤りと犯罪性の第二は、それがどんな新たな社会的富も生み出すことがない、ただ富を消費するための行為だという点にある。
一般に、投資家が国債購入と引き換えに政府に貸し付けたおカネは、政府が様々な企業の生み出す商品やサービスを購入することに費やされるのであって、何か新たな社会的富を生産するために用いられるのではない。その一部が、ときに社会的に有用な目的のために支出されることがあったとしても(これさえ本来は資本の負担で行われるべき)、多くはむしろ社会的な富の浪費と食いつぶしのために用いられている。しかも特に、それが軍備に充てられる場合は、何の富も生み出さないどころか、その富の浪費と食いつぶしの最悪の形態、富と人命の破壊のために備えられ、用いられるという事であり、社会の福利にとっては巨大なマイナスと損失を意味する。
軍拡のための増税だけでなく、軍拡のための借金拡大=MMT軍拡にも断固反対しよう!(A)
アソシエーション論の過去・現在そして未来
世界を見渡せばいわゆる独裁国家、権威主義的国家と言われるものが増大しているとされます。とはいえ、市民的権利や人権のために恐れ知らずに闘う市民運動や過酷な搾取に抗う労働運動の再建も試みられています。
レスター・サラモンが、NPOなど非営利経済組織が先進諸国では労働人口の5%に拡大していると書いたのが20世紀末の事でした。彼はそれを「アソシエーション革命」と名付けました。
われわれワーカーズもまた、二十世紀末より、田畑稔氏や特に大谷禎之介氏らに学びながらマルクスの「アソシエーション論」を深めてきました。この過程で段階的にまとめたのが「アソシエーション革命をめざして」「アソシエーション社会」という基本文書です。(ワーカーズ・ホームページで閲覧できます。「新聞ワーカーズ」でも検索が可能です。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さらに、これらの文書とわたしたちの議論の内容を煮詰めたものが以下の通りで「ワーカーズ・ホームページ」の左側に掲載されています。
■ 国家・行政部分の縮小をつうじて国家中心社会を転換し、自己決定権にもとづく当 事者主権社会をめざします。
■ 市場原理と成長至上主義の企業中心社会と決別し協同組織や連帯行動を拡げ、持続 可能な循環型の協同労働社会をめざします。
■ 政府・行政に依存した福祉制度から脱却し、共助・連帯ネットワークの拡大をつう じて、福祉コミュニティーをめざします。
■ 国益主義や偏狭なナショナリズム、軍事優先主義を克服し、国境を越えた労働者・ 生活者の連帯で、アジアと世界の間で善隣友好関係を築いていくことをめざします。
■ 労働者・生活者の運動をつうじて規制・決定力を強化し、均等待遇をはじめとする 権利を拡大していくことをめざします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この一年間でもアソシエーションをテーマにした記事は三本あります。「気候危機とアソシエーション革命について」(22.2.1号)、「〈新しい資本主義〉 対置すべきは《アソシエーション社会》」(22.1.1号)、「私がアソシエーション社会を確信したとき」(同)。
このようにその後の歴史的展開や新たな経験に基づき、より質の高い運動が求められており、会員がそれに応じた考察をしてきました。
しかし、基本文献である「アソシエーション革命をめざして」からすでに二十年が経っており、会員全体の問題として議論をしてゆくことが必要だと私は思います。会員のみならず「ワーカーズ」読者のみなさんのご意見なども聞かせていただきたいものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
気候危機、ジェンダー問題、新自由主義との闘い・・様々な課題と向き合うばかりではなく、同時に未来社会の基本的イメージも含む運動としての「アソシエーション」の思想的な普及と発展を期待しています。(A)
「沖縄通信」・・・「沖縄で日米共同統合演習(キーン・ソード23)」
東京新聞が1月18日の「こちら特報部」で、米シンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS)が公表した台湾防衛の机上演習を取り上げた。
最も可能性が高いとされる基本シナリオでは、「中国軍の死傷者は2万2千人に上り、3万人以上が捕虜となる」と指摘。一方で、台湾防衛に成功しても「日米中の対戦により、米軍は2隻の原子力空母と最大20隻の艦船が撃沈され、最大372機の航空機を失い、最大1万人の死傷者が出る。参戦する自衛隊も、112機の航空機と26隻の艦船を失う」と、双方に甚大な被害が出ることを予測している。
軍事ジャーナリスト小西誠氏は「艦船の被害想定は米軍と同規模かそれ以上の場合もある。自衛隊にも米軍と同規模の死傷者が出かねない」「最初は、東シナ海を中心に海洋限定で戦闘が進んでいく。直ちに核戦争にいくことはないだろうが、米中の軍事的な決着がつかない以上、数年掛けて二会戦、三会戦とどんどん激しくなる。最終的に全面戦争や核兵器の使用に向かっていく可能性は否定しきれない」と指摘する。
ご存知のように、自衛隊が南西諸島に配備されているのは奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島、与那国島で、石垣島以外の駐屯地は完成している。さらに米軍は、南西諸島にある約200島のうち40島を海兵隊の拠点にする計画を進めているという。
今日の報告は、昨年の11月10日~19日まで、沖縄本島ばかりではなく南西諸島を含んで大規模な日米共同統合演習(キーン・ソード23)が実施された。
この日米共同統合演習は過去にない大規模な演習であった。
以下は沖縄の知人からの報告を紹介する。(富田英司)
<沖縄からの報告>
★日米共同統合演習「キーン・ソード23」
大規模な日米共同統合演習(米軍によるコードネームは「キーン・ソード23」)が11月10日から19日まで、自衛隊26,000人、米軍約1万人、両軍の航空機約370機、空母を含む艦艇約30隻を動員して実施された。オーストラリア軍、カナダ軍、英軍も加え、NATO(北大西洋条約機構)軍もオブザーバーとして初めて参加した。
浜田防衛相が会見で発表した内容によると、「あらゆる事態に即応するための抑止力・対処力を強化するとともに、日米の強固な意思と連携を示すことで、わが国の防衛及び地域の平和と安全の確保に寄与していく」とのことだ。一言でいうと、「台湾有事」や「尖閣有事」を念頭に、武力攻撃かどうか判別が困難なグレーゾーン事態から「武力攻撃事態」に至るまでいかなる事態にも対応できる対中国戦争の予行演習であると言える。
★中城湾港に自衛隊200人と車両73台が上陸
キーン・ソード自体はほぼ2年に1回実施され、今回で16回目となるが、今回の最大の特徴は公然と沖縄を舞台に民間の港湾・空港・道路も演習場所としたところにある。防衛省統合幕僚監部は演習の開始に備えて、事前に兵員・装備を輸送した。11月8日午前、民間チャーター船「はくおう」が鹿児島港―名瀬港を経て、県が管理する中城湾港に自衛隊員約200人、車両73両を陸揚げした。「はくおう」は民間チャーター船とはいっても、実は全長200m、最高速力30ノットの性能を保持する自衛隊・米軍専用の軍用輸送船である。
8日朝、平和市民連絡会・うるまをはじめ各地の島ぐるみのメンバー約200人は、自衛隊員と装備の陸揚げに反対して、はくおうが接岸する岸壁前第4ゲートに結集した。ゲート前には、「沖縄を再び戦場にするな!」「日米共同統合演習を中止せよ!」「自衛隊は中城湾港の使用をやめよ」などの横断幕やプラカードがあふれた。
陸揚げされた各種自衛隊車両は港の新港地区にズラリと並べられた。その光景は、民間港は有事には自衛隊が使用するという軍事優先の姿そのものであった。
自衛隊車両の通行を阻止するためにゲート前に座り込んだ人々を警察機動隊が強制排除した後、自衛隊車両は長い列をつくって国道を南下し那覇基地など各地の自衛隊基地へ向かった。
★台湾に最も近い島・与那国で日米両軍が戦術調整
与那国島では、防衛省が示した資料によると、自衛隊40人と米海兵隊40人による「日米連絡調整所」の設置訓練が行われ、通訳を交えて自衛隊員と海兵隊員が共同で作業する有様がテレビで放映された。米軍の与那国での訓練は初めてだ。琉球新報によると、この合同訓練は米軍の発表では「二国間陸上戦術調整センター」と記述され、那覇、奄美、さらに熊本にも設置され、地図を見ながら戦術のすり合わせを行なったという。
11月17日、県が管理する民間空港である与那国空港を使用して、陸上自衛隊の16式機動戦闘車(MCV)を九州から空輸する訓練が実施された。MCVは戦車である。違いはキャタピラーに変えてタイヤを装着しているため、道路上の移動がたやすいという点である。105ミリ砲を搭載する戦闘車はその後、地元住民の抗議を無視し、県道216線をゆっくりと走って陸自与那国駐屯地に入った。この日の抗議行動には、与那国だけでなく石垣からも駆け付けた。MCV翌日、陸自与那国駐屯地から与那国空港へ県道216号線を自走し、空自輸送機に積み込まれ離陸した。与那国に滞在したのはわずか一日に過ぎないが、県の管理する民間空港を使用して輸送し県道を自走するという事自体が実践的な予行演習だった。(沖縄K・S)案内へ戻る
川柳2023/2 作 石井良司(カッコ内は課題句です。)
埋められる鶏に捧げるレクイエム
ヒロシマの根回し非核口にせず
打ち出の小槌これぞ新資本主義
攻撃は防御と増やす防衛費
四年目もまだ顔パンツ外せない
パンダに託す日中の縺れ糸(「糸」)
袖の下糸がほつれる五輪服(「糸」)
国債の孫への転嫁見ないふり(「逃げる」)
金継ぎの技に鍋島蘇る(「豪華」)
コンクリの川に鰻が消えていく(「川」)
したいことあれこれ余生忙しい(「輝く」)
フクシマの時計を止める汚染水(「計」)
温暖化残りはわずか砂時計(「計」)
殺処分罪なき鶏へ花手向け(「飾る」)
脱炭素行司も仕切る待ったなし(「行司」)
愛の夢育てたなおみママになる(「スタート」)
ウィズコロナ舵を切らせた白い紙(「スタート」)
フクシマを忘れたフリの再稼働(「スタート」)
遊ぶ子の笑み再びとウクライナ(「幸」)
コラムの窓・・・危うい原発復権のたくらみ!
糸の切れた凧のように空高く漂う岸田文雄氏は、手あたり次第にあれこれ広言しています。無能な政治家が自己顕示でしゃべっているだけならさして問題ないのですが、彼が内閣総理大臣として権力を握っているのだから、穏やかではありません。とりわけ、原発の再評価は核をもてあそぼうという無謀な方針転換です。
GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議によると、安全確保を大前提とした運転期間の延長など既存原発の最大限活用するとし、これまでに再稼働した原発10基に加えて7基の原発の再稼働する。さらに、次世代革新炉の開発・建設まで行おうというものです。岸田首相はこの重大な方針転換をいともたやすく行い、実行に移そうとしています。
この方針転換に関する4件のパブリックコメントが年末始に行われていたので、私は4件すべてに、頑張って意見を送りました。恥ずかしながら、その内2件を紹介します。パブコメなんて形式だけかもしれませんが、嫌味なども含めて言いたいことを書く送って読ませるだけでも、送ったもの勝ちというものです。
原子力規制委員会宛て「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要(案)に対する科学的・技術的意見の募集の実施について」
原子力発電という装置も、おのずから製品としての寿命があります。
あらゆる製品には製品としてのサイクルがあり、初期のトラブルが克服されたら、その後は部品交換等の整備によって安定的な働きをするでしょう。しかし、寿命が尽きてきたら故障が重なり、いずれ役割を終えて廃棄となります。物質である限り、そのサイクルを越えて延命させることには限界があるのです。
その視点から考えるなら、原発の寿命は30年とか40年でしょう。慎重な稼働、整備を行っても、40年稼働が妥当なところだと思います。さらに20年延長というのは、例外的に付け加えられたものであり、安全側の視点より経済的打算に重きをおいた判断ではないでしょうか。稼働していない期間においても、とりわけ原発は他の装置に増して、その劣化は避けられません。安易に休止期間をなかったことにするのは、あまりにご都合主義にすぎます。
私は、寿命の尽きた原発は例外なく廃炉にすべきだと考えます。規制委は設置された経緯が明確にされているのだから、その初心に帰り、あらゆる思惑から離れたところで、安全規制に特化した働きをすべきです。
原子力委員会あて「『原子力利用に関する基本的考え方』改定に向けた御意見の募集について」
原発安全神話の崩壊から学ぶべきは、脱原発しかないという事実です。
3・11以前は原発の過酷事故は起こらないとされていたので、適切な事故対応ができないまま多くの市民が被曝し、それまで築き上げてきた生活や社会関係を失いました。その後の対応、汚染地の無人化や避難の基準は意図的に緩くされており、健康への配慮がありません。
とりわけ、事故炉の廃炉は困難に直面しており、実際上は不可能と言うほかありません。何より、デブリの取り出しはできるはずもなく、出来たとしても置くところがありません。放射性物質が外部に漏れないようにして、そのままにしておくほかないでしょう。
アルプス処理水と言われている放射能汚染水の海洋放出は、犯罪行為に等しいものです。薄めても捨てられる放射性物質の量は変わらないし、それが濃縮されて帰ってこないという保証はないでしょう。
安全神話崩壊から学ぶべきは、放射能汚染されたごみを増やさないこと、それを拡散しないこと、閉じ込めることに全力をあげることに尽きます。そして、避難をよぎなくされ、健康の不安を抱えた方々に全力で補償を行うことです。間違っても、原発活用などと言うべきではありません。(晴)案内へ戻る
色鉛筆・・・無罪あるのみ
死刑囚とされたままの袴田巌さんは86歳。不当な逮捕からすでに57年もの間、裁判のやり直しを求め続けている。
1966年6月、旧清水市の味噌製造会社専務一家4人殺人放火事件の犯人とされるも、一貫して無実を訴えて再審を求めている。2014年に静岡地裁がやつと再審開始を決定、48年ぶりに身柄も釈放された喜びもつかの間、9年近くたった今もなお再審は開かれていない。理由は検察による抗告と、続く東京高裁の再審請求棄却決定(2018年6月)。
袴田さん側の特別抗告により、最高裁は2020年12月に高裁決定を取り消し、審理を高裁に差し戻し今に至っている。
最高裁が「犯行時の着衣」とされた衣類の血痕の色に争点を絞って審理を差し戻して2年、高裁での審理は昨年12月に終わり、今年3月に再審開始の可否を明らかにするという。弁護側の主張は、血痕は味噌の中で1年以上も赤みを保つことはあり得ない。衣類は発見直前に何物かによって仕組まれた捏造の証拠である。即刻再審開始、無罪とすべき。一方検察側は、独自に1年2ヶ月間味噌漬け実験をし「条件によっては赤みが残る」と主張、袴田さんの再収監をも求めている。
左の表は、1966年8月18日の逮捕から9月19日に「自白」するまでの警察及び検察当局によって提出された取り調べの時間だ。休むこともトイレに行くことさえ許されず拷問を受け、自白を強要され続けた。ボクシングで鍛えた頑健な心身も(殺されるかも知れない)恐怖と、無力感に陥り意識が朦朧とする中「自白した」とされた。
しかし事件をごく普通に見ても、おかしな点が多過ぎる。1人の人間が一度に、どう4人もの人を殺せるのか?しかも凶器は、刃長13.6センチのクリ小刀一つ。4人の傷は総計41ヶ所(74ヶ所とも)でめった刺し。住み込み従業員だった袴田さんは上告趣意書に「柔道三段の被害者専務が出張・外泊日は従業員に判っているのに、専務不在の時を狙わずに行われた殺人・放火事件は怨恨によるものに間違いない」と書いている。
さらに自白では犯行時の着衣がパジャマのはずが、1年2ヶ月後工場の味噌タンクから血染めの衣類(ステテコ・スポーツシャツ・半袖シャツ・パンツ・ズボン)が発見されると、これが決定的証拠であるとされた。ところが当時の袴田さんは、これで晴れて無罪になると喜ぶ。なぜなら事件当時履いていた自身の履き物には血が付いておらず、血染めの衣類とはつじつまが合わない。自分の服にはクリーニングの「ハカマタ」のネームが付いているのに無い。ズボンは小さくてはけない等々・・・。
しかし半世紀以上たつ今も、不正な裁判のもと死刑判決は維持されたままだ。
元裁判官の木谷明氏は講演で、「冤罪を生まない裁判をめざして、被告人の言い分に耳を傾け、争いのある点については徹底的に事実審理を尽くす。最終的には『疑わしいときには被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則に従って裁判をする」と述べている。
袴田さんは、30歳での逮捕からのち57年もの間、こうした裁判に一度として出会うことがかなわなかった。今なお再審無罪を求め闘い続ける姿からは、今年3月、東京高裁がどう決定を出すかにかかわらず、司法とともに私たち自身に対しても様々な問題が投げかけられていると感じる。
一日も、一刻も早い無罪判決を!再収監は決して許さない!(澄)
★集会案内
『3/19袴田巌さん応援大会』ー今度こそ袴田さんを無罪にー
・ 日時 3月19日(日)13時30分から16時30分
・場所 アクト研修交流センター62研修交流室
・ゲスト 望月衣塑子さん
『4/1再審開始決定報告集会』ー検察官の特別抗告をみなんで阻止しよう~
・日時 4月1日(土) 13時30分から16時頃
・場所 静岡労政会館6階ホール (再審請求棄却の場合中止の可能性もあります)
案内へ戻る